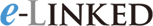

LINKED plus シアワセをつなぐ仕事
「私の使命は、患者さまとそのご家族が抱く、
"自宅で療養したい"という願いを叶えること。
専門家が一丸となれば、その思いはきっと実現できる」。
木股美由紀
新生訪問看護ステーション・アウン 所長/
社会医療法人 大雄会
愛知県一宮市にある社会医療法人大雄会。
同法人が運営する新生訪問看護ステーション・アウンには、
17年間にわたり訪問看護の現場を見続けてきたベテラン看護師がいる。
病棟勤務から"患者本位の看護"に惹かれて訪問看護の世界へ。
そこに待っていた病棟看護とのギャップに戸惑いながらも走り続けてきた。
「私の役目は、患者さまとご家族の自己決定を尊重し
安心して在宅療養が継続できるよう支援すること」だと語る彼女。
そこには、病院と地域を繋ぐ訪問看護師の姿があった。


「家に帰りたい」。終末期を迎えた患者とその家族の"最期の願い"を叶える。それが訪問看護に課せられた大きな役割のひとつだ。愛知県一宮市にある社会医療法人大雄会。同法人が運営する新生訪問看護ステーション・アウンの所長・木股美由紀看護師は、病院での勤務を経験後、17年にわたり訪問看護を続けてきた。いわば草分け的な存在だ。訪問看護に長く携わりながら、利用者やその家族の思いと真摯に向き合ってきた。
終末期の患者が病院を退院し安心して自宅に戻るには、さまざまな準備が必要となる。自宅近くの医療機関をはじめとする他職種のスタッフとの連携、介護保険の申請、介護を行う家族の受け入れ態勢など、すべての環境を整えるには時間がかかる。ただ、木股看護師は言う。「本当に一丸となれば、短時間での在宅療養への移行は可能です」と。「在宅医療に関わる専門スタッフがそれぞれの能力を発揮して集結すれば、もっと早期に退院ができる。私が携わったなかでも、余命1~2週間の末期がんの患者さまに、連絡を受けた2日後には環境を整え退院していただけた例もあります」。
本人の希望を尊重して早期に在宅へと移行する。そのためには病院や地域の他職種のスタッフとの協働が不可欠となる。よりよい協働をしていくには、療養者やその家族中心の理念や情報の共有、信頼関係の構築が重要だ。在宅で協働する一員として手腕を発揮するのが木股看護師のような在宅看護のスペシャリストだ。「ご本人がご自宅で安心して療養生活を過ごせるよう支援すること。それが私の役割です」と話す。
最近では核家族化が進み、"老々介護"の家庭も少なくない。独居の高齢者も増加の一途をたどる。こうした高齢者は、最終的には施設に入るしかないのだろうか。ただ、厚生労働省の終末期医療に関する調査によれば、実に国民の6割以上が自宅での療養を望んでいるという。「本当はできる限り家で過ごしたい」。そんな願いを叶えるために、木股看護師の奮闘は今日も続く。


木股看護師が訪問看護師になった17年前は、まだ訪問看護が制度化されて間もない時代。病棟勤務時代、家族と看護師が信頼関係を築き、一緒に患者を見守っていく姿に"看護の原点"を感じていた彼女にとって、家族と手を携えてケアにあたる"利用者本位"の訪問看護は、まさに求めていたものだった。
しかし当初は、病棟と在宅の間にある大きな環境の違いに戸惑いがあった。木股看護師が感じた病院と在宅の一番の違い。それは「看護のあり方」である。「病院ではどうしても、"患者さま中心"の個別性のある看護というわけにはいかなかった。一方、訪問看護では、現場はご自宅。すべてが"ご利用者さま中心"の、個別性の高い看護が求められます」。そしてさらにと、言葉を続ける。「ご利用者さまのご自宅には、病院では当たり前に揃っている医療機器や用具はなく、もちろん医師、先輩看護師などの医療スタッフもその場にはおりません。そのなかでどう問題を見極め、判断し、看護を実践するのか。また、使用する物品についても病院のように安易に使うことはできません。ご利用者さまのなかには、今より物資の少ない時代を経験した方が多く、ものをとても大切にされます。その感覚にあわせたコスト意識を養う必要もありました」。
木股看護師が聞いた話では、とある訪問看護師は、療養者の家族から突然に訪問看護を断られたという。その理由は「自宅に訪問した際、玄関に脱いだ靴を揃えなかったから」。在宅医療の提供者である前に、一人の人間としての常識やマナー、接遇の質までもが問われるのだ。「本当に専門性と人間性が試される仕事。『この人になら看てもらいたい』と思っていただけることが肝心です。それだけに、評価していただけたときの充実感と喜びも大きいですね」と木股看護師は話す。


今後の課題の1つに、後継者の育成がある。新生訪問看護ステーション・アウンでは、採用基準を実務経験5年以上と定めている。「在宅では看護師が身近な相談相手となることが多く、医療に関する制度や介護保険などの知識も求められます。ご利用者さまの病状、医療依存度、生活背景は多種多様で、安心して在宅療養を継続していただくには幅広い知識・技術を提供しなければなりません。だから医療現場経験者が好ましいのです」と木股看護師は吐露する。
もちろん、急性期病院で医療技術を学ぶなど、充実した研修カリキュラムや新卒の訪問看護師をフォローできる体制が整備できれば不可能ではない。しかし、現実的には難しい。とりわけ小規模の訪問看護ステーションでは、常勤の看護師が3名という施設もある。そのなかで1名を研修に出すことやフォローを行うことが果たして可能だろうか。
後継者を育成するシステムをどう構築していくのか。今後の大きな課題といえるだろう。


2013年1月、新生訪問看護ステーション・アウンは、総合大雄会病院の近くに移転した。これにより、病院と連携しながら、後継者を育成しやすい環境ができた。と同時に、退院支援の看護師などとの関係性が深まり、病院と地域を繋ぐ役割を果たす訪問看護ステーションが、より継続性を持って医療を提供できる状況ができ上がった。
総合大雄会病院・医療相談室の医療ソーシャルワーカー、長尾貴子は言う。「在宅への退院支援で肝心なのは"医療の継続"です。地域の診療所の先生方にどのように引き継いでいくのか、また医療依存度の高い患者さまの場合は、訪問看護ステーションとどう連携しながら動くのかが重要になります」。在宅に移行すれば、地域の医療機関に日々の診療を依頼することになる。そのためにも「地域の先生方の信頼に足る病院であることも大切」だという。「重要なのは『何かあれば大雄会に相談できる』という体制を築くこと。こうした安心感を患者さまにも地域の医療機関にも持っていただけるようにしたいです」。
また、在宅医療を円滑に進めるためには、病棟看護師が「在宅を知る」ことも重要だ。病棟に勤務する看護師が在宅での生活を見る機会は少ない。退院後の具体的なイメージを持つことは至難だ。今回、訪問看護ステーションが病院に近づいたことで、互いが理解しあい、"看護師同士の距離感"が縮まることにも木股看護師は期待している。
「私たちの中期ビジョンは、マグネットステーションになること」と木股看護師は言う。「ご利用者さまとそのご家族、看護師、地域の医療機関・事業所が、磁石のように吸い寄せられるような場所でありたいですね」。幕を開けたばかりの新天地で、彼女は理想のステーション像に想いを馳せる。
COLUMN
BACK STAGE