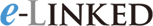

LINKED plus シアワセをつなぐ仕事
私は、この街で、看護師として成長したい。
母として命を育みたい。
増尾亜貴子(救命救急センター)/
地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院
「転職して良かったとすごく思いました」
看護師としてのキャリアを伸ばすこと。母として輝き続けること。
多くの看護師がその仕事人生のなかで、一度は直面する二律背反する課題。
「私はどちらも叶えたい」と考えた増尾亜貴子看護師は
転職を決断する。彼女の〈諦めない〉挑戦は、ここから始まった。


岐阜県立多治見病院(岐阜県多治見市)の救命救急センター。真剣な眼差しで患者を見守る一人の看護師がいる。増尾亜貴子。1年間の育児休暇を終えた後、復職。今年2月から時間短縮勤務制度を活用し、仕事と子育てを両立させている。
「本当は怖かったんです。どんどん職場に戻る日までのカウントダウンが進んでいって。そのときが来ちゃった...みたいな感じでした」。育児休暇を終え復帰が間近に迫った頃を増尾は振り返る。「一年間休んでいて、看護師であることを忘れるくらい子育てしかしてなくって。ちゃんと看護師やれるかな。時短勤務で私が職場に戻るのって、みんなは迷惑じゃないかな」。そんな増尾に看護部長の柘植容子は「救命救急センターのみんなが待ってるから戻りなさい。自分が無理できないときは、助けてもらって、自分が返せるようになったら返せばいいのよ。順番、順番」。その言葉が、増尾に勇気を与えた。そして復職当日を迎え「お帰りって感じでした。案ずるより産むが易しでしたね」と増尾はうれしそうに話してくれた。


増尾は、以前、名古屋市内の救命救急センターで働いていた。27歳で結婚、子どもがほしいと考えるようになった29歳。「結婚して、出産を考えたとき、前の病院でも育休とか産休とか支援してくれる制度はあったんです。でも、あまりに忙しく、余裕のない当時の職場の状況を考えたとき、私がこれらの制度を上手く使い、子育てしながら看護師を続けていくイメージがどうしても持てなくって」。彼女は決断した。「地元に帰ろう!」。真っ先に思い浮かんだのが、岐阜県立多治見病院だったという。面白さがわかってきた救急看護をさらに深めたいと考えたのだ。しかし、岐阜県立多治見病院の救命救急センターは、東濃医療圏全域を少数精鋭のスタッフでカバーする地域の最後の砦。迅速な判断処置が求められる部署で看護師の力量も問われ、高いスキルを身につけるための勉強も求められる。彼女の〈母になる〉という目的を考えたとき、前の職場で感じたような迷いや不安は生じなかったのだろうか。「はい、感じませんでした。先輩たちの存在が大きかったと思います」と増尾は当時を振り返る。「母として、夜勤もバリバリやって、時短勤務などの制度も上手く使いながら。そしてそれを応援する病院の空気感がありましたから、これなら私もやれるって思いましたね」。


少子高齢社会のなかで、地域医療は急速に変化している。増尾が勤務する急性期病院は、多くの重篤な患者を受け入れるために入院期間の短縮が求められる。結果、しわ寄せが看護業務に転嫁され、看護師への負担が重くなっていく。看護師を疲弊させる変化が、看護師不足が叫ばれるなか、離職を誘発する。病院は先に挙げた産休制度や時短勤務などのさまざまな制度を作り、看護師を支援している。しかし、制度利用を希望する看護師が周囲の状況を気にする余り、使うことに躊躇するような環境では、せっかくの支援策も意味をなさないのではないだろうか。


増尾は「私は恵まれている」と感じているという。プライベートでは、看護師と子育ての両立を応援してくれる家族がいる。増尾と同郷だった夫は、増尾と同じタイミングで岐阜県内に転職。地元に戻り、親のサポートも得られるのは、夫婦2人だけの子育てよりも何倍も心強いという。そして職場には、都会から地元に戻って働いている看護師も多く、結婚して戻ってきた増尾に、「もうそろそろ子ども欲しいでしょ」と気さくに話しかけ、増尾がこれからの計画を伝えても、嫌な顔をする人は一人もいなかったという。「自分の生活があっての仕事だよ」という仲間の温かい思いと応援が、増尾の〈母になる〉という決断を後押しした。
柘植看護部長によると、そんな岐阜県立多治見病院にも、看護師不足と医療の変化による看護師たちの疲弊が影を落とすという。だが、取材の最後に増尾は明るい笑顔で「私がいきいきと看護を続けることで、『出産しても続けられる』と考えてくれる人が増えてくれるはず」と言う。さらに「地元でちゃんと看護を学びながら働ける。この働きやすい病院の空気感や風土を維持するためにも」。
「私は、自分の育ったこの街で、看護師であることを、そして母であることを続けます」。
「家族がいて、親戚がいて、幼馴染がいて、不謹慎な話だけど、知り合いの誰かが亡くなると、すごくみんなが集まるんです。ほんと、湧いて出るみたいに」。増尾は窓に目線を向けながら、「都会で働いてるときは、感じなかったなあうん、やっぱり地元で、働きたい」。
COLUMN
BACK STAGE