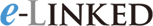

LINKED plus 病院を知ろう
医療と生活を繋ぐ現場へ。
新たな環境のなかで生まれた、
医師と看護師の気づき。
西尾市民病院
1年前、高度急性期病院から赴任してきた循環器内科医。
2年前、急性期病棟から地域包括ケア病棟へ異動になった看護師。
以前とは異なる環境に入り、戸惑い、悩みながらも、覚悟を決めていった2人。
彼らの気づきを通して、西尾市民病院が今、どのように変わろうとしているか探った。


循環器内科医の吉田雅博は、平成29年、県内の高度急性期病院から西尾市民病院に赴任してきた。前の病院では研修医時代を含め、トータル7年間勤務。循環器内科で急性心筋梗塞に対する緊急カテーテル治療や重症の心不全に対応するなど、多くの経験を重ねてきた。そこから同院に移り、何が変わっただろうか。「自分で診療する範囲が広がりました。以前は、すべての診療科が揃った大病院だったので、他の疾患については専門医に相談すればよかったのですが、ここでは診療科も医師の数も限られます。循環器の範囲を超えて自分で判断することが増え、最初は戸惑いましたね」と話す。また、同院では、患者を生活の場に繋ぐ役割も担う。容態が落ち着いてもすぐに帰れない患者は、地域包括ケア病棟(詳しくはコラム参照)へ転棟し、退院に向けて準備をするのだ。その場合、吉田が引き続き主治医となって、患者の退院まで見守る。「地域包括ケア病棟は、全く初めての経験でした。そこで要求されるのは、循環器内科というよりも、一般内科医の役割ですね。患者さん、ご家族の思いを聞いて、病棟スタッフと一緒に退院後のゴールを定め、できる限りおうちに帰れるように支援しています」と吉田は話す。


吉田が関わる地域包括ケア病棟の師長を務めるのが、稲垣元子看護師である。急性期の外科病棟に長く勤務していた稲垣だが、2棟目の地域包括ケア病棟の立ち上げとともに異動した。「打診されたときは、『え、私が?』と思わずつぶやきました。それまで急性期の病棟で、患者さんの急変に対応しながら、忙しく立ち働くのが好きだったんです。そこと真逆の環境ですから、不安が大きかったですね」と振り返る。それから1年余り、稲垣は迷いながら、求められる病棟看護のスタイルを模索してきた。どんな気づきがあっただろうか。「まず、時間の流れが180度変わりました。以前は、絶えず時間に追われていましたが、それは今思えば、医療者側の都合でした。ここは、退院後の生活を想定し、患者さんの生活リズムに合わせて、食事やトイレの介助をしていくことが求められます。また、退院支援がうまくいかず悩む場面も多いですね。急性期のように治癒を目的にするのではなく、複雑な問題を解決していかなくてはならない病棟です」と稲垣は話す。
吉田医長は「これからの医師は、専門医であっても、生活への視点が欠かせない」と言う。「主治医は、治療して終わりじゃないと思います。患者さんが退院して、どんな生活に戻れるのか。むしろそっちのマネジメントが大事。ですから、患者さん、ご家族とできるだけ話すように心がけています」。


吉田と稲垣が直面する環境の変化は、西尾市民病院が地域の人々から変化を迫られている状況をよく表わしている。超高齢社会を迎え、医療の中心は病院から在宅へ移行しつつある。同院は従来のように、二次救急と専門医療に対応するだけでなく、今後はコモンディジーズ(頻回に発生する一般的な病気)への対応や、在宅療養を支援する視点を持ち、高度な急性期治療を終えた患者を生活の場へとスムーズに繋ぎ、在宅療養中に急変した患者を受け入れる役割まで担う必要がある。


そうした地域のニーズを現場で受け止め、2人は自分の意識を違う方向へと向けてきた。吉田は気持ちの変化について次のように話す。「高度急性期病院で循環器内科医として勤務していたときから、私は、カテーテルの手技など自分の専門性を高めることに注力してきました。そして今も、市民病院として、地域で発症する循環器疾患全般に最先端の知見に基づく診療を提供したいと日々勉強しています。でも今はこういう医師のあり方も悪くないかな...と。循環器内科を軸にしつつ、退院支援までサポートするような関わり方が、意外と自分に合っているのかなという感じがしています」。
一方の稲垣はどうだろうか。「私の場合、気持ちの切り替えに時間がかかりました。正直、まだ急性期の看護に未練もあり、こんな私の指導で良いのだろうかと悩むときもあります。ただ、少しずつやりがいも見えてきました。患者さんの思いを聞き、他の医療職と力を合わせて、患者さんとご家族が望まれる生活へ送り出すことができると、本当に良かったと安堵します。今後はスタッフ教育に力を入れ、市民の皆さんの期待に応えられるよう、病棟の看護力を高めていきたいですね」と話す。西尾市民17万人の生活を守るという高い目線を持ち、現場の模索と挑戦は続いていく。
稲垣師長は、患者の思いを知るには「観察が大事」だと話す。「たとえば、ベッドサイドに持ち込まれた物品から、その方の嗜好や生活をイメージしたり、ご家族が面会に来られたときの表情から関係性を想像したり...。注意深く観察して、患者さんに寄り添う看護をするようスタッフに指導しています」。
COLUMN
BACK STAGE