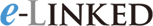

LINKED plus シアワセをつなぐ仕事
痛みをコントロールして
その人らしい生活を
取り戻すために。
緩和ケア認定看護師 奥村利恵
一宮市立市民病院
平成30年10月9日、一宮市立市民病院に、
尾張西部医療圏では初めての緩和ケア病棟が誕生した。
その病棟の立ち上げに参加し、現在、同病棟に勤務する、緩和ケア認定看護師の奥村利恵。
奥村が志向する緩和ケア病棟のあり方や、緩和ケア認定看護師の役割について話を聞いた。


一宮市立市民病院の緩和ケア病棟は、新棟の5階。病室はすべて個室タイプで全14室。どの部屋も大きな窓から明るい光が差し込み、心地いい環境が整えられている。この病棟は検査や治療を行わず、身体的、精神的苦痛を和らげることを目的としたところ。フロアには、ゆったりした穏やかな空気が流れている。
「ここでは、病院というより、生活の場に近い雰囲気づくりを大切にしています。たとえば、コーヒー好きの方には、ボランティアさんの協力を得て、ティーサービスを提供しています。患者さんの痛みが和らいで穏やかな表情を見せてくれたり、中庭に出て、ご家族と楽しそうに歓談している様子を見たりすると、この病棟ができて本当によかったと思います」。そう語るのは、緩和ケア認定看護師の奥村利恵。奥村は平成28年から始まった緩和ケア病棟の準備プロジェクトに参加し、理想の病棟づくりに情熱を燃やしてきた。奥村がめざしたのは、どんな緩和ケア病棟だったのだろう。


「どうしても譲れなかったのは、ホスピスのように、看取りだけの場所にしないこと。そうではなく、症状が辛いときに入院し、痛みをコントロールして、また生活に復帰していただく。そんな病棟にしたかったんです」。その願い通り、現在、緩和ケア病棟の入院目的は、看取りが50%、それ以外が50%。家族の介護疲れをいやすためのレスパイト入院を含め、多様な目的で利用されている。「退院後も安心して暮らせるよう、退院支援部門のスタッフやがん相談支援センターとの連携を日頃から大切にしています。まだ開棟後間もなく、課題もありますが、看護師長をはじめ、病棟スタッフと相談しながら、患者さんにとってより良いケアを模索しています」と、奥村は話す。
奥村は現在、緩和ケア病棟で入院患者を支えるかたわら、緩和ケアチームの一員として組織横断的に活動。さまざまな病棟から依頼を受け、多職種から成る専門チームで入院しているがん患者の辛い症状の緩和に尽力している。また、毎週木曜日は〈緩和ケア外来〉の担当看護師として、在宅で療養しながら、通院しているがん患者と家族の相談に応えている。まさに、緩和ケア認定看護師の専門性をフルに発揮し、がん患者と家族の身体的、精神的、社会的苦痛の緩和に尽力している。


奥村が緩和ケア認定看護師の資格を取ったのは、平成27年。以前からがん性疼痛や緩和ケアに興味を持ち、自主的に研修を受けて知識を深めてきた。「がんの治療中は、痛みや吐き気、息苦しさ、だるさなどさまざまな症状がでます。それらの辛さを薬物療法でコントロールできる人もいますが、そうでない人もいます。薬物療法と合わせて、マッサージなどの看護ケアを加えることで、苦痛が和ぐこともある。がんの辛さを軽減するには、私たち看護師がちゃんと学び、エビデンス(科学的根拠)に基づく看護を実践すべきだと考えたんです」。


約半年間の通学で、奥村は大きな気づきを得たという。「それは、〈認定看護師が特別な存在になってはいけない〉という教えです。患者さんを看るのは現場の看護師。私たちだけが専門家なのではなく、すべての看護師が同じような専門性を発揮できなくては意味がないと考え、スタッフの指導に力を入れています」。具体的には、各病棟に1名ずついるリンクナース(緩和ケアチームと病棟看護師を繋ぐ看護師)を集めて、勉強会を開催。また、緩和ケアの〈院内認定看護師〉の養成にも力を注ぐ。これは、緩和ケアに興味を持ち、所定のレベルをクリアした人を認める制度だが、現在11名に増えた。「そういったコアなメンバーを中心に、院内で緩和ケアを広めていきたいです」と奥村は言う。さらに奥村は、緩和ケア教育を、地域の施設や訪問看護師へも広げていきたいと意欲を見せる。「がんの痛みさえ取れれば、家に帰りたい、という方がすごく多くいらっしゃいます。そういう方々が在宅に戻り、自分のやりたいことができるように、地域の方々と一緒に力を尽くしていきたい」。奥村は緩和ケアの伝道師として、がんと共に生きる人々を支えていく。
奥村が看護師として大切にしている思いは、孤独のなかにいる患者に寄り添うことだという。「自分で痛みを訴えられる方はいいのですが、そうでない方や身寄りのない方は、一人で苦しみに耐えています。そういう方々の辛さを見逃さないよう、しっかり時間をとってお話しするよう心がけています」と話す。
COLUMN
BACK STAGE