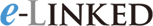

LINKED plus 病院を知ろう
地方独立行政法人
岐阜県総合医療センター
最先端のパルスフィールド
アブレーション治療に取り組む。


心房細動に対するカテーテル治療は、今まさに転換期を迎えている。これまで主流だった〈高周波アブレーション〉に代わり、〈パルスフィールドアブレーション〉が登場したのである。その最先端治療が行われると聞き、岐阜県総合医療センターを訪ねた。
カテーテル室に集まっていたのは、循環器内科医、看護師、臨床工学技士たち。全身麻酔をかけ、循環器内科医が治療用のカテーテルを太ももの付け根から血管を通じて心臓に挿入。熟練の臨床工学技士たちが心電図をリアルタイムで解析し、循環器内科医とともに目標とする心筋組織を探していく。「ここで間違いないな」。全員で確認すると、短時間の周期(パルス)で高電圧をかけ、問題の組織だけを選択的に細胞死へと導く。心臓の不規則な信号が確実に改善したことを確認し、治療は終了した。
この新しい治療法のメリットはどこにあるのか。「何よりも安全性の向上です。従来のように高周波の熱を使わず電圧を用いるので、食道などの周囲臓器や神経にダメージを与えるリスクが大幅に低減しました。これにより、リスクの高い高齢患者さんにも手術を勧められるとともに、私たち術者のストレス軽減にも繋がっています」と話すのは、不整脈科部長の割田俊一郎である。


同センターがパルスフィールドアブレーション治療を導入したのは2024年11月。日本で保険適用になった2024年9月から2カ月以内というスピード導入だった。
この経緯について、割田は次のように語る。「パルスフィールドアブレーションは欧米ではすでに標準的な治療法だったので、早くから論文などで情報収集し、一刻も早く地域の皆さんに提供したいと考えていました。保険適用後はトレーニングを受けたり、大学病院に症例見学に行ったりして、万全の準備を整えました。幸い、当科は2024年、不整脈治療の専門医が着任し、専門医2名プラス不整脈の専門医をめざす若手医師の3名体制で、マンパワーも十分にあります。同時に、臨床工学技士や看護師のトレーニングにも力を注ぎ、最先端の治療をチームで支える体制を構築してきたのです」。


割田たちが心房細動の治療に力を注ぐ背景には、高齢化に伴う高齢患者の増加がある。では、心房細動とはどのような病気なのか。「心房細動は、心臓の中にある心房が小刻みに震えて痙攣する疾患です。直接命に関わる病気ではないのですが、怖いのは心不全を起こしたり、心房内の血栓が血流に乗って脳に運ばれ、脳梗塞を引き起こすリスクが高まることです。脳梗塞になれば、命に関わることはもちろん、麻痺や言語障害の後遺症から生活の質が著しく下がることになります。ですから、心房細動が見つかれば、できる限り早く治療することが重要です」と、割田は話す。そんな割田にとって、パルスフィールドアブレーションはまさに念願の導入だったという。「安全性がより高まったので、今まで手術を躊躇されてきた高齢の方も〈頑張ってみようか〉と思っていただけるようで、とてもうれしく感じています」(割田)。


さらに2025年6月より、院内の環境も著しく向上した。本館地下に、カテーテルアブレーション治療専用室が新たに稼働し、週5日間体制で治療が可能となったのだ。「従来はアブレーション治療を希望されても、2〜3カ月、お待ちいただくのが常でした。でも、これからは待ち時間を大幅に短縮できますし、それだけ患者さんとご家族に喜んでいただけると思います」と、割田は期待を寄せる。また、アブレーション以外でも最先端の技術が次々に導入されている。たとえばペースメーカーの治療では、カテーテルを用いて心臓内に本体を留置する〈リードレスペースメーカー〉などもいち早く提供してきた。「名古屋や東京の病院に行かないと、新しい治療を受けられない。そういうことがないように、これからも私たちは常に技術を高めて、世界標準の不整脈治療を提供していきます」。割田は力強く語った。
COLUMN
BACK STAGE