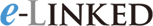

LINKED plus 病院を知ろう
みよし市民病院
病気の早期発見こそ私たちの使命。
高い志をもって検査に取り組む診療放射線技師たち。


昨年の晩秋、みよし市民病院・放射線技術課にうれしい知らせが届いた。放射線技師の吉田美香が、マンモグラフィ画像のコンテスト(第34回日本乳癌検診学会学術総会企画マンモグラフィポジショニングコンテスト)で優秀賞を受賞したという知らせだった。このコンテストはマンモグラフィの撮影技術向上を目的に毎年開催されているもので、高精度の撮影に欠かせないポジショニング(乳房の向きや位置を調整すること)の技術を評価する貴重な機会となっている。吉田に話を聞いた。
「もともと放射線技術課では、〈マンモグラフィ検診施設・画像認定施設(※)〉の取得をめざしていて、その過程で自分たちが撮影した画像についても問題点や改善策を検討してきました。その成果として、提出した画像が思いがけず表彰されて本当にうれしかったですね。仲間と喜びを分かち合いました」。
※NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構が、マンモグラフィ検診の撮影装置や写真、X線線量などを評価して認定している。


マンモグラフィは乳房専用のX線撮影で、複数の方向から乳房を板で圧迫し、薄く伸ばした状態で撮影する。とくにむずかしいのはどんなところだろうか。「マンモグラフィの目的は、乳がんのごく早期に生じる、乳腺の石灰化(小さなカルシウムの沈着)を見つけることですが、小さく淡い石灰化を見逃さないために、やはりポジショニングの高い技術が問われます。装置の性能に加えて、自分たちの腕がしっかりしていないといい画像を撮影できない、すごく繊細な検査なのです」と、吉田は説明する。
マンモグラフィで疑いが見つかれば、エコー検査や細胞診といった精密検査で、乳がんかどうか総合的に判断される。もちろん良性のこともあるが、乳がんはごく初期に見つかれば90%以上完治する病気でもある。マンモグラフィはまさに、乳がん治療の入り口の役割を担っているのだ。吉田はこのマンモグラフィのほか、レントゲン、CT、MRI、エコー検査などを幅広く担当。それぞれの検査に求められる撮影技術を磨くために、勉強会や講演会、学会にも積極的に足を運んでいる。


吉田が入職したのは13年前。以前は2つの施設で勤務していたが、診療放射線技師の責任ややりがいを強く認識するようになったのは、ここに来てからだという。吉田の意識を変化させた要因は何だろうか。
「多分、患者さんの生活に思いを向けるようになったからだと思います。当院は市民の健康や生活を守るという強い信念があり、それが院内のスタッフ全員に浸透しています。そうした環境に身を置くことで、自然と患者さん一人ひとりに寄り添って、病気の早期発見に貢献したいと思うようになりました」(吉田)。


吉田が話すように、同院は市民の生活に密着した市民病院として、市民の健康づくりを支えている。高度な急性期医療に特化した大きな病院ではないし、外来機能だけのクリニックでもない。両者の間にある医療機関として、高度急性期医療と生活を繋ぐ役割を担う。たとえば、同院の検査で病気の疑いが見つかり、より専門的な治療が必要と判断されれば、速やかに高度急性期病院へ紹介される。その一方で、クリニックから患者の紹介を受け、詳しい画像検査や診断を行うことも多い。医療と生活を繋ぐ病院だからこそ、検査部門の果たす役割は重要で、果たすべき責任もひときわ大きい。
「当院では、私たち技師は単に撮影するだけではありません。画像を見て何か緊急の疾患が疑われる場合、すぐ主治医に連絡するところまでの役割を担っています。それだけ大きな責任を感じています」と吉田。万が一、精密検査で病気を見逃すことがあっては、患者さんのこれからの人生にリスクを与えることになる。だからこそ、高いモチベーションをもって、医師も診療放射線技師も日々の検査・診断に取り組んでいるのだ。「市民の皆さんに〈市民病院で早めに検査して、本当に良かった〉と思っていただけるように、私たちはこれからも検査技術を磨いていきます」と吉田は語った。
COLUMN
BACK STAGE