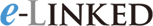



新緑のある日、西尾市民病院の手術室では〈転移性肝がん〉の手術が行われていた。転移性肝がんとは、別の部位のがんが肝臓に転移して増殖したものである。手術を担当したのは、執刀医のほか、禰宜田政隆院長をはじめ数名の外科医たち。手術後の肝機能の温存を考慮し、がんのできている部分とその周囲をできるだけ小さく切除。転移したがんをきれいに取り去り、無事に手術を終えることができた。
この患者(70代・男性)はもともと数年前に大腸がんと診断され、同院で手術と抗がん剤治療を受けていた。しかし、診断時にはすでに進行しており、手術でがんを取り去ったものの、目に見えない小さながん細胞が体内に散らばっている可能性があった。そのため、治療後も定期的に検査を続けてきたのだが、今回、とうとう肝臓への遠隔転移が確認されたのである。


「一般に、がんの再発や転移が見つかると、もはや完治は望めず、抗がん剤による延命治療が行われます。でも、大腸がんからの転移性肝がんの一部は、外科的切除によって生命予後の改善が見込めることがわかっていて、今回も幸運なことに手術適応となりました。患者さんは転移が見つかったとき、かなりショックを受けられたようですが、〈決して諦めることはないですよ〉と、主治医や看護師たちに励まされ、手術を決断されました」と、禰宜田は説明する。70代という年齢もあり、手術が決まったときから、退院後の生活サポートにも力を注いだという。
「ご高齢の場合、入院するとどうしても体力が衰えます。入院中からリハビリテーションを行うと同時に、ご本人とご家族に、退院後の食事や軽い運動方法などを学んでいただきました」。また、高度急性期病院などでは臓器別に異なる医療チームが担当するが、同院では大腸から肝臓に変わっても、同じ担当スタッフが関わってきた。「初発のがんのときから患者さんに関わり、病歴や生活環境をよく知るスタッフが周囲で支えるので、安心して治療にのぞんでいただけたと思います。そして、実はこういう対応こそが、当院のがん診療の強みだと考えています」と禰宜田は振り返る。


禰宜田が患者に寄り添うがん診療こそ強みだという背景には、時代とともにがん治療が変化してきたことがある。その昔、〈がんは不治の病〉と考えられ、〈命を救う〉治療が最優先され、病巣部を徹底的に切除する手術療法が主流だった。しかし、抗がん剤治療や放射線療法、手術療法が進化を遂げ、がんへのアプローチ方法が多様化。がん種ごとに有効な治療法が確立され、今やがんにかかっても、多くの人が生き延びられる時代になった。
「以前はがんだけを診て治療すればよかったんですが、それでは患者さんの本当の幸せには繋がりません。私たちに求められるのは、がんとともに生きる患者さんを支えること。少し専門的な表現をすると、〈ディジーズ(医療者がイメージする病気)〉よりも、〈イルネス(患者がイメージする病気)〉に視点をおくことが重要だと考えています」と、禰宜田は話す。


ディジーズ(disease)もイルネス(illness)も、広い意味では〈病気〉を表す英語である。しかし、禰宜田はあえて2つを区別し、より患者の立場で病気と治療を見つめようというのだ。「特殊ながんについては専門的な施設での集中的な医療が必要になりますが、一般的ながんについては、がんの治療とその後のケアをトータルに支えていく医療が求められます。私たちの使命は、まさに後者の医療。2人に1人はがんになる時代だからこそ、イルネスの視点を大切に患者さんを支えていきたいですね」と、禰宜田。
その考え方を裏づけるように、同院では、訪問看護ステーションの開設に向けて、準備も始まっている(詳しくはコラム参照)。「訪問看護ステーションの開設により地域の在宅医療に携わる方々とさらに連携を深めながら、市民の皆さんの生活をしっかり守っていきたいと思います」(禰宜田)。
COLUMN
BACK STAGE