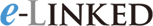

LINKED plus 病院を知ろう
岡崎市民病院
外科・内科をはじめ、多職種が連携し、
チームで肥満症治療に取り組む。


初夏のある日、岡崎市民病院の肥満症治療センターで、内科医、外科医をはじめ、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、臨床心理士など多職種が集まり、患者の治療方針について活発に意見を交わしていた。最初に議題に挙がったのは、腎臓内科に通院中の40代男性である。肥満の指標である体格指数(BMI)は54.4と非常に高い数値を示しており、慢性腎臓病、脂質異常症、高血圧症など複数の健康問題を併発している。この患者は6カ月ほど前から食事療法と運動療法を軸にした肥満症治療を開始し、定期的なフォローアップを受けてきた。管理栄養士と理学療法士は、これまでの食事や運動療法の成果を報告。
続いて内科医である滝啓吾(肥満症治療センター副センター長兼内分泌・糖尿病内科部長)が生活習慣改善を目的とした行動療法の経過を伝え、患者のモチベーション維持や日常生活での継続性について議論を交わした。当初は順調に減量できていたが、最近は停滞が見られ、腎機能などの指標にも改善がない。「次の段階として薬物療法や外科療法を検討する時期ではないでしょうか」と滝が提案。外科医の石山聡治(肥満症治療センター長・腹腔鏡手術・減量手術センター長兼内視鏡外科部長)もこれに同意し、「手術適応もありますので、ご本人の生活や希望を考慮しながら治療方針を決めましょう」と応じた。


肥満症治療センターでは、毎月こうした多職種によるカンファレンスを開催している。2024年のセンター設立に先駆け、同院では2014年から愛知県内でも先進的に肥満症治療を実施してきた。「最初は外科が中心でしたが、食事や生活習慣の改善には内科をはじめとする多職種の協力が欠かせません。滝先生の赴任を機に、外科・内科、多職種の協力体制を整え、センター設立に至りました」と石山は経緯を語る。
肥満と肥満症の違いについて滝は、「肥満は単に脂肪が過剰蓄積した状態ですが、肥満症はそれによって健康に支障をきたした状態で、BMIが35以上の場合を高度肥満症と呼びます。肥満症は動脈硬化の原因となり、心筋梗塞や脳卒中などの重篤な病気を引き起こすため、減量が必須です」と説明する。


肥満症治療では、食事療法や運動療法、行動療法で十分な効果が見られない場合、薬物療法または外科療法が選択される。近年の薬物療法では〈持続性GLP -1(ジーエルピーワン)受容体作動薬〉や〈持続性GIP/GLP -1(ジーアイピー/ジーエルピーワン)受容体作動薬〉という新薬が承認され注目されている。これらの薬剤はGLP -1、GIPというホルモンの作用を通じて食欲低下による体重減少効果を期待できる。「新たな薬剤の登場で肥満症の治療の選択肢が増えました。患者さんと相談しながらそれぞれの患者さんに最適な治療法を選んでいます」と滝は話す。
一方、外科療法では、腹腔鏡を用いて胃の一部を切除する〈スリーブ状胃切除術〉が保険適用で実施されている。「生活習慣や薬物療法で思うように成果が出ない方や、リバウンドを繰り返している方には手術療法が有効です。その決断をサポートすることも私たちの役目です」と石山は語る。


内科と外科、多職種が連携して、着実に治療実績を積み重ねる肥満症治療センター。今後の展望について滝は「メディカルスタッフに対して、日本肥満学会が認定する〈肥満症生活習慣改善指導士〉の育成も進めたいと考えています。多職種スタッフを肥満症の専門家として育て、三河地区の肥満症治療をリードする専門チームを作り上げたいと思います」と抱負を述べる。
さらに石山は次のように続けた。「地域医療連携にも力を入れていきたいですね。地域には、糖尿病や腎臓病などの治療をしていてもなかなか成果が出ない方がいらっしゃいます。そういう方々を診療所の先生方からご紹介いただくことで、生活習慣病の治療効果を高めて、地域の皆さまの健康増進に貢献していきたいと思います」。
COLUMN
BACK STAGE